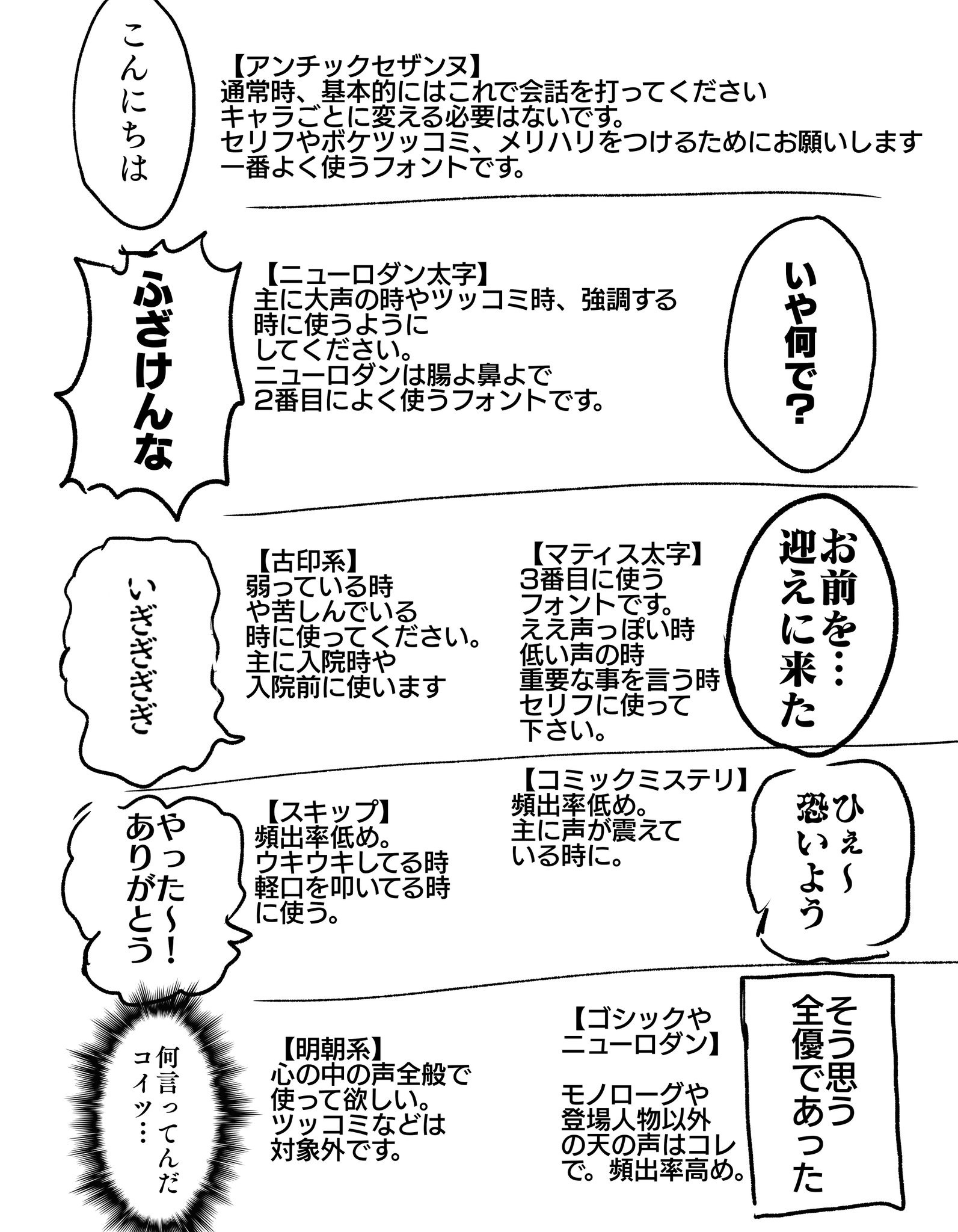こんにちは、営業部・安藤です。
「フォントを巡る冒険」第4回は、米国で大ベストセラーとなったアレックス・バナヤン著『THE THIRD DOOR』の日本語版出版に携わった、株式会社東洋経済新報社の笠間勝久さん、佐藤朋保さん、橋爪朋世さんにお話を伺うべく、日本橋にある東洋経済新報社の本社を訪ねました。
先日のサントリーコミュニケーションズ・西川圭さんへのインタビューは、デザインという言葉の深淵さを感じ、営業という身ながら自身の仕事に対するスタンスを顧みる、そんな貴重な機会となりました。前回の商品デザインから、今回は本の装丁デザインへ。同じデザインという言葉でも作法が全く異なる世界を旅します。マーケティング、編集、装丁とそれぞれの担当から見た、他国のベストセラーを日本にローカライズして世に広めていくスト―リーを是非お楽しみ下さい。

笠間 勝久(かさま かつひさ)
ビジネス系出版社を経て、東洋経済新報社に入社。書籍・雑誌・webの広告・宣伝・企画・プロモーションに携わる。2015年より書籍プロモーションを担当。主に手がけた書籍は『ワーク・ルールズ!』『ライフ・シフト』『SHOE DOG』『the four GAFA』『サードドア』など。

佐藤 朋保(さとう ともやす)
東洋経済新報社に入社し、書籍編集を担当。2012年より翻訳書を中心に手がける。最近編集を担当した本は『ワーク・ルールズ!』『ライフ・シフト』『SHOE DOG』『サードドア』など。

橋爪 朋世(はしづめ ともよ)
東洋経済新報社に入社し、雑誌広告の企画制作に関わる。その後、書籍部門に異動しブックデザインを中心とした業務に従事。『サードドア』のほか、『SHOE DOG』『両利きの経営』『人生はどこでもドア』などを担当。
「本の価値を社会にどう伝えていくか」という視点を大切に
―― 本日は取材を受けて頂きありがとうございます!『サードドア』日本語版、反響大きいようですね。
笠間:ありがとうございます。おかげさまで、各方面からたくさんの反響を頂いてます。
―― 「母の子宮から出てきたときに、僕のお尻にはMD(医学博士)のスタンプが押されていた」と著者であるアレックス・バナヤン氏が第1章で回想する通り、ペルシャ系ユダヤ人の移民の子として米国で生まれ、両親に医者になることを期待されて大学まで無事辿り着くも、入学早々人生の方向性を見失い大学の寮の部屋の天井をじっと見つめる。その後、「人生の答え」を探して自ら成功者にインタビューすることを思いつくところまで含めて、「これは、自分の物語だ」と直ぐに思いました(笑)。読み始めて早々、私のような感想を抱いた日本の読者も多かったんじゃないかと思います。『サードドア』日本語版が出足好調な要因かな、と。
笠間:ビジネス書は分かりやすい成功譚を描くのが通例ですが、『サードドア』は大学生が成功者に突撃インタビューを試みるという構成からして面白く、そのプロセスにおける成功も失敗も包み隠さずに書いている。人間の営みを淡々とした目線で捉えたのがユニークでした。ノンフィクションだけど小説のような読み口で読者をぐいぐい引き寄せますし、「成功とは?失敗とは?」という人生の根源的なテーマにまで立ち返るような内容になっている。従来のビジネス書とは毛色が大きく違っていると感じますね。

―― 一方で、御社が『サードドア』のような書籍を取り扱うことにある種の新鮮さを覚えました。
佐藤:日本の成長軌道や価値観が従来から変容するなかで、「生き方」の本が徐々にフィーチャーされてきました。当社はビジネス書、経済書の版元としてカテゴライズされるケースが多いですけど、『ライフ・シフト』のような生き方と働き方がハイブリッドになった本、そのセグメントに現在チャレンジしています。従来的なビジネス書市場と自己啓発書市場の狭間でどうポジショニングしていくかを模索している最中です。
―― チャレンジングな試みを続ける御社の特長として、出版局のなかにプロモーション部を置いているとのことですが、狙いはどういったところにあるのでしょうか?
笠間:意図としては、編集担当、プロモーション担当といった従来的な定義に捉われず、「伝える視点を大切にしよう」ということです。本作りに際して、版権を買い付けるところからプロモーションの現場まで一気通貫、同じスタンスで行っています。本の価値を社会にどう伝えていくか、社会にどう「共振」するかをシームレスな関係性のなかで徹底的に考えることが出来ています。
今回の『サードドア』で言うと、米国を背景としたこの本をどういう風に日本の読者に届けるか。日本社会の伝統と文化の有り方、リアルタイムの社会の「呼吸」みたいな部分をどう設計していくかというところで、『サードドア』チームとして、会社全体を巻き込む形で一丸となって取り組めました。作品の本質的な価値は勿論有るけど、一方で日本人はどういった部分に価値を感じやすいか、その感じやすさの部分もスピード感を考慮して、入口ではこう感じるけど深いところではどう感じるか、浸透の速度含めて編集担当とマーケティング担当とが一緒になって考えて、それを装丁へと繋いでいったという流れです。
―― 部署間での密な連携の下でリリースした『サードドア』が、日本でここまで反響を呼んだ理由はどこにあると思いますか?
笠間:「日本人はメンタリティ的にサードドアを叩けない」なんて言われているけれど、自分らしい人生を掴もうとする著者の勇気が日本人の心にも訴えるものがあったのだろうと考えています。米国発信の本ではあるけれど、結果的に現代の日本人が渇望するものを提示できている。その上で装丁もコンセプトを見事に体現したものになっていて、ハマりすぎるくらいハマってますね(笑)。
佐藤:本文ページのレイアウトは当初の想定とは全く違った形になりました。プルーフ版(事前の宣伝に使うために最終原稿の原稿を使って、仮に印刷・製本した見本本)を4パターンくらい作りました。何度も変更を加えて、組版をしてくれた編プロさんには相当ご迷惑をおかけしましたけど(笑)、最後の最後にコンセプチュアルなデザインが出来上がった。本当に苦労した甲斐がありましたね。
装丁デザインが購入動機に直結する現代
笠間:ちなみに、『サードドア』の装丁で使われているこの書体は何という書体ですか?
―― 「筑紫オールドゴシック」という書体です。橋爪さんが装丁を担当された書籍では、以前から本当に良く使って頂いている書体なんです。
橋爪:困ったときの「筑紫オールドゴシック」ですから(笑)。

笠間:(『サードドア』の装丁を指さして)この「精神的資産のふやし方」というサブタイトルは、佐藤たちとコンセプトワークを数ヶ月に渡って繰り返して、本当に頭が擦り減るくらい推敲して作ったんです。(サブタイトルにも使用されている)筑紫オールドゴシックは、親しみやすくて身近な感じだけど精神的な価値が表出していて、凄く良いですね。深さを感じさせるフォントだと思います。
―― 嬉しいお言葉、ありがとうございます!
笠間:マーケティングの側面から見ても、ネット書店や電子書籍が隆盛の昨今だからこそ、購入動機に直結する装丁の重要性を感じています。特に『サードドア』は、日本ではまだ名の知られていない青年が書いた本。そうなると、パッケージが一層重要になってくる。読者を引っ張って連れていく、その役割を今回は装丁が果たしてくれた。完全にパッケージの勝利だと思いますね。
佐藤:外形的には若者向けですけど、大人の方にも読んでもらえる誂えになっていますよね。

―― 原書(『THE THIRD DOOR』)の装丁は全面黒、日本語版は全面白となっています。装丁が原書と異なる点についても、詳しく教えてください。
笠間:日本語版のコンセプトは「明るい墓標」。原書の装丁は黒の扉を開いたようなデザインになっている。美しい一方で、秘密の扉を開いたようなイメージを持たれる可能性も有ると考えました。この本のコンセプトは失敗や地味な挑戦の連続の先に成功がある、トリッキーでマジカルな扉はないというものです。真摯で真っ直ぐな感じを表現したかった。白色にしたことで、ストイックな神聖さをストレートに表現できたと思っています。
―― 装丁を担当された橋爪さんとしてはどのようにお考えでしょうか?
橋爪:私のこの白色の解釈は「光」。原書のカバーにある扉を開けたところの光にフォーカスしました。私は日本語版カバーのカラフルな部分をスペクトルと勝手に呼んでいるんですけど、光が重なっていくと白色になるように、原書と色味は違うけど光を扱っている本という意味では繋がっていると感じています。
―― 日本語版のもうひとつの特長として、原書が『THE THIRD DOOR』と全て大文字で表現したのに対して、日本語版は『The Third Door』と大文字表記を一部に留めました。何故でしょうか?
橋爪:使用したフォントの並びの良さですかね。大文字で並べたときに少し攻撃的な感じがしたし、単語自体が目に入ってきて、読むというより見て伝わると思ったんです。
笠間:ビジネス書は「これで成功します」といったコンセプトを前面に出す本が多いですが、『サードドア』は成功法則を押し付ける本ではないので、よりシンプルに作りたかったんです。著者も一歩引いた美学を持って中間的なものに価値を置いてますし、単語の頭文字だけ大文字にして正解かなと私も思いますね。

―― 橋爪さんにお聞きしたいのですが、先ほどの笠間さん、佐藤さんのお話のように『サードドア』出版に向けて装丁面での苦労はなかったでしょうか?
橋爪:特にはなかったです。(装丁に際して)私のなかにあるものを出している感覚はなくて、答えは皆さんのなかにある。今回も私のなかで悩むことはなかったですね。
―― そもそも、デザインに行き詰まったりすることはないんですか?
橋爪:そうならないように、そして何よりキチンと理解するために、まず「聞く」姿勢を大切にしています。
―― 素晴らしい心掛けですね。そんな橋爪さんのインスピレーションの源は?
橋爪:移動しているときかな。歩いたり、旅行しているときとか。
―― 今度は笠間さん、佐藤さんにお聞きしたいのですが、橋爪さんと他の装丁家さんとの違いを感じる瞬間って有りますか?
笠間:我々のコンセプトワークに橋爪にも参加してもらうんですが、常に根源的なことを聞いてくる。参加者の思っていることを受け止める力や感度も抜群に高いんです。何より、勉強熱心ですよね。今でも書店によく行っているし、ビジネス書だけでなく文芸書まであらゆるジャンルの本をしっかり見ている。(橋爪さんは)数年前まで雑誌広告を制作する部署にいたのですが、コンセプトをエディトリアルデザインにどう落とし込むかという作業をずっと行ってきたので、そのときの経験が今に生きているのでは、とも思います。
佐藤:ビジネス書って流行の「型」がありますけど、橋爪が普通の見方をしていないので、他の本とは明らかに一線を画してますよね。『サードドア』も白さが際立つ本で独特の存在感を放っていて、書店に積んであっても非常に目立ってます。今では書店発信のSNSにも、装丁担当者として橋爪の名前が著者、訳者と併記されるくらいですから(笑)。我々の思い描くコンセプトを必ず形にしてくれて、一緒に仕事しやすいですね。

―― 橋爪さんご自身、装丁家になる未来を想像されていましたか?
橋爪:文字はもともと好きでした。小学生のときにノート取ったりするときも、構成を妙に気にしたり、見出しとか飾り付けちゃったりして。先生から「算数の授業中だから。そういう時間じゃないから」と怒られたりしてた(笑)。振り返ってみればそういった延長線上に今があるのかな。
―― 素敵なエピソードですね。何だかジーンとしました。
「それは、失敗によって得られるものだ」
―― 『サードドア』のお話を改めて。日本語版の出版(2019年8月23日)から1週間経ちましたが、今の手ごたえを教えて下さい。
笠間:成功の物語を読みたくて手に取ったけど成功法則が書いていないという人もいれば、なんでもない日常を淡々と描いているところに深いメッセージを感じ取る人もいる。読者に依って拾うところや受け取り方が全然違う。現時点で書店、ネット、SNSの反響が従来と比較にならないくらい大きくて、議論の的になっている。これで良いと思っています。ロングセラー、永遠に読み継がれる本とはそういう本だという確信が有ります。
佐藤:翻訳エージェントから『サードドア』の情報を頂いてから約2年、長い時間をかけてここまで辿り着いたことは素直に嬉しいですが、本が出版されて終わりでは決してない。本の価値を社会にどう伝えていくか、引き続き考え続けていきたいと思います。
―― 最後に個人的なお話をすると、私はクインシー・ジョーンズ(Quincy Jones, 1933-)へのインタビューの章がこの本で一番のお気に入りです。
クインシーは僕に新たな欲求をインストールしてくれた。僕の人生の1つのステージが終わって、新たなステージが幕を開けようとしている気分だった。
会話が終わる頃に、「僕は生まれ変わったみたいです」と言った。
「今夜あなたは、僕が学べるとは思いもしなかったことを教えてくれました」
「それは何かな?」と彼は聞いた。
「完全な人間になること、この世界を知る1人の人間になることです」
「すばらしいな、そのとおりだよ。ナット・キング・コールはいつも私にこう言っていた。『クインシー、君の音楽には人間としての君がそのまま反映される』とね」
「それは世界を回って得られるものですよね」
「そうじゃない」と言ってクインシーは、僕の意見をこう正した。
「それは、失敗によって得られるものだ」
僕はクインシーがこの言葉を何度も繰り返しているみたいに感じた。僕の中にゆっくりとしみ込んでいくのを待ちながら。
(第34章「伝説のプロデューサー」より)
音楽界で最も偉大なキャリアを持つと言われる伝説的なアーティスト、プロデューサーの彼が、殊更に成功を勝ち誇るのでなく、失敗にむしろフォーカスしている。バナヤン氏本人もこのインタビューを経て、成功/失敗の軸ではなく、挑戦(成長)の観点から人生を俯瞰するようになっていく。
笠間:しっかり読み込んで頂きありがとうございます。バナヤン本人もクインシー・ジョーンズへのインタビューのところが一番好きって言ってましたよ。
―― それは嬉しいです!私自身、これまでの成功/失敗に捉われることなく、前を向いて挑戦を続けていきます。本日は、貴重なお話をありがとうございました!

After Recording 取材を終えて…
数年前に『LETS』を新規ご契約頂いた後、東洋経済新報社の書籍では筑紫書体の使用頻度が圧倒的に増えました。その旗振り役であった橋爪さんに『サードドア:精神的資産のふやし方』の装丁にて「筑紫オールドゴシック」をご使用頂いた縁で、今回の取材と相成りました。
取材を終えて、今改めて『サードドア』日本語版の奥付を見ると、「装丁:橋爪朋世、プロモーション担当:笠間勝久、編集担当:佐藤朋保」とお三方の名前がしっかりと刻まれています。シームレスでフラットな関係性のなかで、より良いものを生み出すべく出来ることを全てやり切る出版局のエース・笠間さん、会社からヒットを期待されて実際にヒットを量産し続ける佐藤さん、そして「産みの苦しみは感じない」と纏う雰囲気さながら軽やかに、そして自然体で見事な装丁を生み出す橋爪さん。まさにオールスター陣容で、今回の取材に臨んで下さいました。
小さな決断によって、誰もが人生を大きく変えることができる。
みんなが並んでいるからと何となく行列に加わり、ファーストドア(正面入り口)の前で待つのも自由だ。
行列から飛び出して裏道を走り、サードドアをこじ開けるのも自由だ。
誰もが、その選択肢を持っている。
これまでの旅で学んだ教訓が1つあるとすれば、どのドアだって開けられるということだ。
(第35章「レディー・ガガ」より)
私自身、今回の取材を通じて『サードドア』という本を知り、サードドアという概念をインストールすることが出来て、本当に貴重な経験となりました。夢のような時間をありがとうございました!

取材日:2019年9月2日
写真=まめぞう